その2
機能性を持つ和音の解説・一覧表2
セカンダリードミナント
「二次的なドミナントコード」の意味で、性格や形態はドミナント7thコードそのものですが、
一つの調の構成音(ドレミファソラシド)では作れない音が含まれています(ノン・ダイアトニックコード)。そのために「二次的な」という語がつけられています。
この記事での割り当てを説明します。
例えばドレミファソラシド=メジャースケール=長音階は、一般に「ダイアトニックスケール」と呼ばれます。
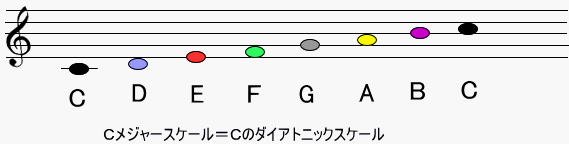
このスケールの構成音を一つ飛ばしの規則で積み上げて和音を作ります。
下記のように色で書き分けるとダイアトニックスケールと、ダイアトニックコードの関係がわかります。


こちらはCマイナーキー(ハ短調)でダイアトニックコードを作った例です。
セカンダリードミナントの解説
CメジャーキーではG7-CM7(V7-IM7)が調を確定するドミナントモーションでした。
これと同じ形をその他のCのダイアトニックコードに対して作るのがセカンダリードミナントコードの考え方です。
Cメジャーキーの7つのダイアトニックコードにドミナントモーション(V7-I)の関係を
作ってみます。
G7-CM7(ドミナントモーション)
A7-Dm7
B7-Em7
C7-FM7
D7-G7
E7-Am7(Aマイナーキーのドミナントモーション)
F#7-Bm7(♭5)
これらの赤字の進行の左側の7thコードをこの記事ではセカンダリードミナントコードとします(解釈に各位の違いがあります)。
A7,B7,C7,D7,F#7です。
これらの流れをコード進行に挟むと豊かな音楽的広がりを作ってくれます。
ただしあまり用いるとしつこくなります。
以下のコード進行で例を見てみましょう。
CM7 |FM7 |Em7 |Dm7 |
Am7 |Dm7 |G7 |CM7 |
こういうコード進行があったとします。音は下記で聞けます。
このコード進行にセカンダリードミナントを挟んでみます。
CM7 C7|FM7(B7)|Em7 A7|Dm7(E7)|
Am7 A7|Dm7(D7)|G7 |CM7 G7|
セカンダリードミナント2 (音はこちらで)
Cのダイアトニックコード以外のコードが多数使用されていますが、コードアナライズ(楽曲分析)的にはキーはCメジャーとされます。常にCのダイアトニックコードに帰結を伴っているからです。これは何で?と考えず、そういう学問だ、と思ってください。科学的根拠などはありません。慣習です。覚えてしまった方が良いです。
楽曲分析の考え方では、セカンダリードミナントは転調とは捉えず、コード進行を補助するコード(二次的な補助コード)と捉えるわけです。
この時
「あれ?C7のところではCメジャーキーではないんじゃないの?」
と感じたあなたは「不定調性論的思考のできる人」です。一般理論を習得したらぜひ拙論(このブログの斜め読みでOKです)を考えてみてください。
で最後に( )のコードも全部弾いてみてください。
CM7 C7|FM7(B7)|Em7 A7|Dm7(E7)|
Am7 A7|Dm7(D7)|G7 |CM7 G7|
セカンダリードミナント3 (音はこちらで)
さすがにこうなると元のコード進行の印象が残っていませんね。
このようにめまぐるしく音楽を行うのがジャズのビバップと呼ばれる表現方法です。
ビバップは「ゲーム」です。ミュージシャンがその日のゆるい演奏仕事を終えた後(当時はまだビバップ的な音楽の仕事はない)とにかく早く弾き分ける技術を競い合ってトレーニングした歴史の名残がBe Bopです。やがてこれはそれ自体がArtになります。
ドッペルドミナント(ダブルドミナント)
これは「二重にドミナントを配置する」という意味で、二つのドミナントコードが連続する状態を指します。
Dm7-G7よりも強い進行感を与える、とされていますが、不定調性論的には「感じ方は人それぞれ」としています。
一つの考え方として、一般学習では教科書に従い、普段自分が感じるときは不定調性論的思考で自分が感じることを感じる、という感覚も持っていただくのも良いでしょう。
例を挙げておきます。
CM7|Am7|Dm7|G7
これを下記のようにします。
CM7|A7|D7|G7
これはドッペルドミナントの連続ですね。
コードを変えてもメロディと違和感がなければ用いてみるのも一興です(大抵違和感あると思いますので、作曲時に活用してみてください)。
この進行の発展形としてドミナントの連続を書いておきます。
C7-F7-B♭7-E♭7-A♭7-D♭7-G♭7-B7-E7-A7-D7-G7-C7
となります。
なお、
B♭7=A#7
E♭7=D#7
A♭7=G#7
D♭7=C#7
G♭7=F#7と表記しても使用する音は同じです。
解釈論者はどちらかに限定しないといけない、と指摘をされることもありますが、あなたが働く現場で指摘されることを優先してください。
置換ドミナント(裏ドミナント)
これはさらにジャズ的なコード解釈の慣習です。
ドミナント7thコードの特性はトライトーン(増四度関係)を持つことでした。
このトライトーン音程は平均律では、1:√2の振動数比です。数学的には美しく、その響きは心がざわざわさせます。
「美しい不協和音」「悪魔の音程」などと呼ばれます。
以下の図を見てください。
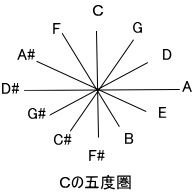
Cの五度圏です。それぞれ対角線に位置するのが増四度の音です。
キーがCのときのドミナントコードはG7です。
このG7に含まれるトライトーンはfとbです。
ではC#7のトライトーンを挙げてみてください。
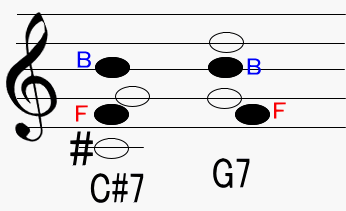
この二つのドミナントコードはトライトーンが等しいですね。どちらのコードもfとbを持っています。そしてc#とgも増四度なんですね。
これが置換ドミナント=裏ドミナントです。
裏ドミナントは「トライトーン構成が等しいので本来のドミナントコードの代理コードとして用いることができる」とされています。
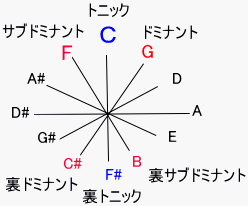
上の図には裏トニック、裏サブドミナントという表記もありますが、一般的ではありません。不定調性論で活用されます。
以下に進行の例を示します。
CM7 |A7 |D7 |G7 |
これは先のドッペルドミナントで示したコード進行です。これを裏ドミナントにしてみましょう。
CM7 |D#7 |D7 |C#7 |
となります。このC#7がCM7に帰着します。「D7は裏にならないの?」もちろんなります。
CM7 |A7 |G#7 |G7 |
これでまた別のコード進行ができました。
これらのコードを弾くときルートをきっちり弾かないと・・・・トライトーンが共通するコードですから、どちらのコードを弾いているか分からなってしまいます。それは実践して確かめてください。
おまけです。
CM7 |D#7 |G#7 |C#7 |
こうなると、裏の裏は表・・・という感じで、あまり効果的に流れません。
そもそも裏ドミナントは「アウトした感じ」を狙い、意表をつく目的があります。
このアウト感が連続すると当然意表をつくことはできない、ということです。
ポピュラーミュージックではエンディングやイントロなどで用いるのが効果的です。
その4へ
参考
和音の進行感についての不定調性論の考え方はこちら。