2018.6.7⇨2020.8.24更新
このトピックについては
こちらも合わせてご覧頂くと嬉しいです。
基音を1とすると、自然倍音の数理によって、オクターブは下記のように分割されていきます。
c
基音
c-c
基音~第二倍音
c-g-c
第二倍音~第四倍音
c-e-g-a#-c
第四倍音~第八倍音
c-d-e-f#-g-g#-a#-b-c
第八倍音~第十六倍音
基音~第二倍音
この範囲をオクターブレンジ1とします。
第二倍音~第四倍音
この範囲をオクターブレンジ2とします。
第四倍音~第八倍音
この範囲をオクターブレンジ3とします。
第九倍音~第十六倍音
この範囲をオクターブレンジ4とします。
この分割は、例えば、顕微鏡で小さいものを見た時に、どんどん視界が拡大されて、より小さい世界が、より大きく見えて、さらなる分割できる素材が見えてくる、そんな状況に似ています。
あとはそれぞれのどの分割のレベルを今用いるべきか、を判断します。
機能和声は、c-e-gが現れることを重視し、ここから音楽を展開しました。
つまり機能和声論は、オクターブレンジ3の前半部分だけを使って作られた音楽理論といえます。
しかしこれがすなわちあなたが用いる音楽とは限りません。
あくまでこれは社会の伝統と慣習から、使いやすさによって浸透していったというだけです。
ハードロックは、パワーコードだけで済む時があります。三度が入るコードを用いると違和感があったりします。
一方ジャズをやるときは、テンションまで細かく考えます。
こうした相違は脳内で処理して分けて考えています。これを和音の「理解の倍率」と表現しました。
不定調性論ではこのオクターブレンジの話を「音の分解能」という考え方に発展させています。それぞれの倍率で適切な音楽を行えば良いのであって、ハードロックは和音がなさすぎて嫌いだ、ジャズはまどろっこしくて嫌い、なんて言う必要はなくなります。その倍率でできる表現を楽しむ、それぞれのジャンルがあるというだけに過ぎません。それぞれ各位がどの倍率の世界を見たいか、興味があるかでやりたい音楽が変わる、と考えれば良いかもしれません。
まずはオクターブも違う音の印象がある、という捉え方にしてみてください。 クルト・ザックス博士が言うように、民族によっては男と女が違う高さで同じ音を歌うと言う認識を持つ場合に、オクターブが同じ音であると認識が伝統として認められていたりもするだけで、それをあなたが受け入れるか受け入れないかは本来自由です。
SNS は見ていれば分かりますが、個人個人それぞれの考えで、それぞれの信念を作品に体現していくだけです。
あとはあなたがどうしたいか、だけです。
この動画の最初のテーマ曲は、レンジ2で現れる音=つまり基音とオクターブ音だけで作った音楽です。一音種を基音を変えて連鎖しています。
それもまた音楽になってしまいます。
なんでもOKなら、あなたは何をやりますか?
人に求められるだけの音楽?
自分が求めるだけの音楽?
社会が求める音楽?
芸術性が求める音楽?
どの分解能で音楽をやるか
を決められれば、あとは好き嫌いと選択の自由です。
One Note Sambaのメロディはレンジ1で解釈した、と理解すれば、他にも様々な表現に対して「機能和声とは違う単位で作った」音楽を探すことができます。
giant stepsも異なる単位で創られた作品と言えます。
長三度が基礎ステップになっている、と無理やり考えることもできるからです。
コルトレーンはそういう思考ではなく、それまでと違うことを、と考えた結果、その「異なる単位」を創造することになりました。
そんな風に考えてみれば、機能和声もある分解能の段階で作られた音楽の1つにすぎない、となります。
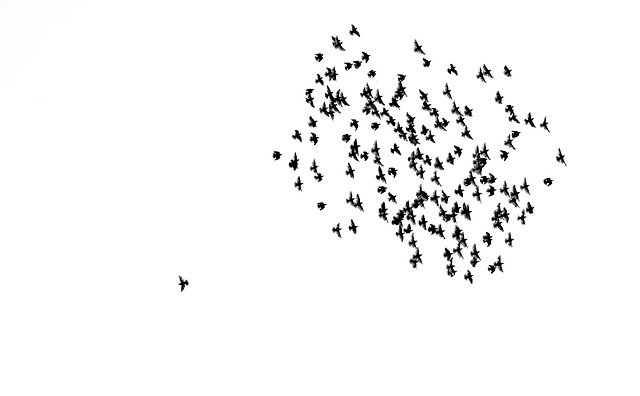
考えているフィールドの切り替えができれば良い
ちなみに不定調性論は上方と下方のレンジ3全体をベースに全てに段階に展開していくことが可能です。自分が今どの感覚にインポーズするべきかを判断し続けます。
ジャズだから、ロックだからその和音を選ぶわけではありません。
クセナキスの音楽を聴く時、園児の歌を聴く時、ロックスターの歌を聴く時、自分が予期している期待感に応えてもらう楽しみがあるはずです。園児の歌にクセナキスの芸術性は求めません。
あなたは普段も理解の倍率をいつも変えているんです。