2018.10.19→2020.2.14更新
関係調の解説
制作作業に直接関係のある知識ではないので、もしピンとこなかった時はどんどん先に進んでみてください。
関係調とは・・・
主音と定められたキー(主調)から近い関係を分類したもので「近親調」とも呼ばれます。厳密な定義のない言葉なので行使によりニュアンスが異なります。
例
Cメジャーキーのダイアトニックコード(三和音)
C Dm Em F G Am Bdim
Gメジャーキーのダイアトニックコード(三和音)
G Am Bm C D Em F#dim
このように類似した和音を持つ調性関係のことを指すことが多いです。
内部に共通する和音を持っていることで、転調がスムーズに行えるなどの利点があります。
主調
その楽曲の基本となる調。(ここではCメジャーを主調にして話を進めています。)
主調は楽曲の多くの部分を網羅しているキーが該当します。
「この曲はCメジャーでキーである」とは主調がCである、ということです。
主調の中心音が主音です。
主調がCメジャーやCマイナーであれば、c音が主音です。
主和音
主調の中心音上に三度堆積で出来る基本的なコードです。
主調がCメジャーキーであれば主和音はC△(メジャー)であり、Cマイナーキーが主調であれば、主和音はCmになります。
Cメジャーキーのダイアトニックコード(三和音)
C Dm Em F G Am Bdim
Cマイナーキーのダイアトニックコード(三和音)
Cm Ddim Eb Fm Gm Ab Bb
同主調(同主長調、同主短調)
主調がCメジャーであれば、同主短調はCマイナーです。
よってCマイナーキーとCメジャーキーは同主調の関係にある、といえます。
主調がCmであれば、同主長調がCメジャー、となります。
つまり同じ主音名の長調(メジャー)と短調(マイナー)の調性関係をが「同主調」の関係です。
これら二つの調から出来るダイアトニックコードが混合されて使用されることで楽曲のコード進行に豊かなバリエーションが生まれます。
Q.
B♭メジャーの同主調は?何でしょうか。答えは本ページ記事下部
平行調(平行長調、平行短調)
主調がCメジャーであるとき、Cから始まる音階をCメジャースケールといますが、この音階はC,D,E,F,G,A,Bという構成音で出来ており、この音階のA音から始まるスケールがAナチュラルマイナースケールであり、これを平行短調と呼びます。
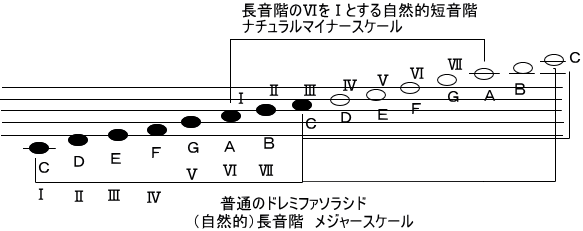
同様にAのナチュラルマイナースケールから見た平行調はCメジャーで平行長調という扱いになります。
構成しているダイアトニックスケールの構成音が等しい調関係が近親調です。
Q.
Aメジャーの平行調は?何でしょうか。答えは本ページ記事下部
属調
主調の完全五度上(完全四度下)の音を主音とした調です。
Cメジャーキーであれば属調はGメジャーキーです。
下属調
主調の完全四度上(完全五度下)の音を主音とした調です。
Cメジャーキーであれば下属調はFメジャーキーです。
その2へ
参考
和音の進行感についての不定調性論の考え方はこちら。
(質問の解答)B♭メジャーキーの同主調はBマイナーキーです。
(質問の解答)Aメジャーキーの平行調はF#マイナーキーです。